251014 未来を創る人材の育成
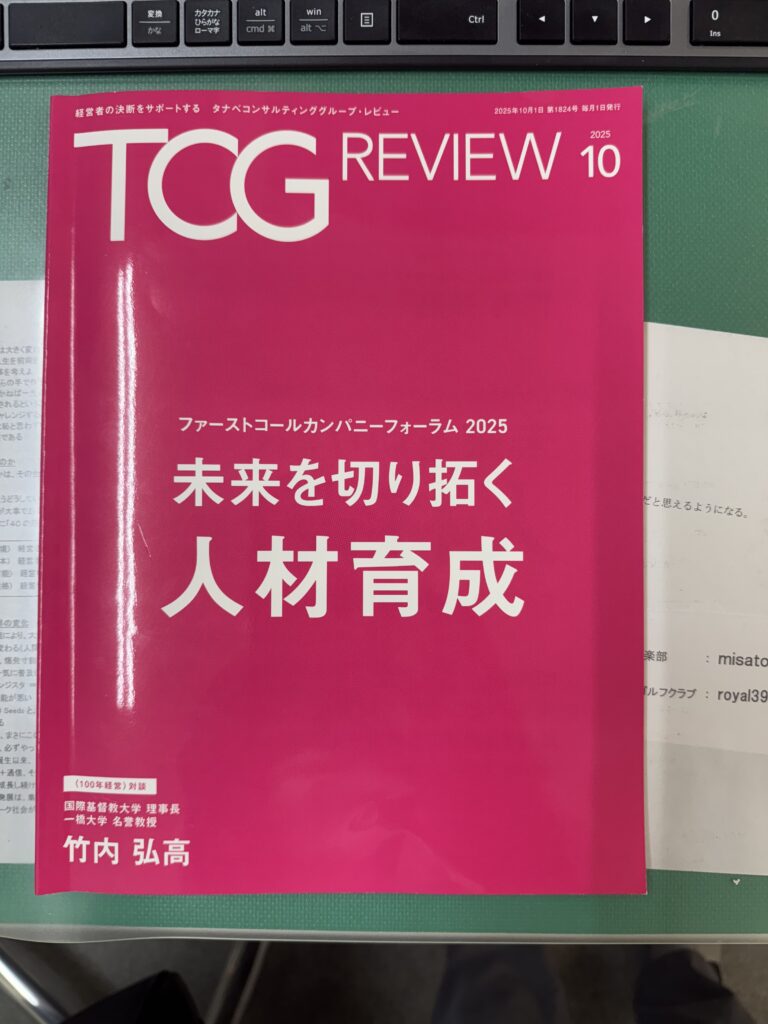
企業が変化の激しい時代を乗り越え、自ら未来を切り開いていくためには、人材という資源をいかに戦略的に捉え、育成していくかが重要です。将来に向け、どのようにリーダーを育て、未来を創る人材を育成していくか、企業の人材育成について説明します。これは単なるスキル研修のレベルにとどまらず、新しい価値観を生み出す経営マインドを持った人材をいかに育てるかという鍵となる話です。未来を担うリーダーに必要な資質は何か、そして企業はどうすればそのような人材を効果的に育成できるのかを考えていきます。政府も2025年2月に「中堅企業の成長ビジョン」を策定し、人材育成のポイントについて言及するなど、社会的な関心も高まっています。
中堅企業は、日本経済の活性化という点において非常に重要な位置づけであり、大きな役割を期待されています。その成長のエンジンとなるのが「人」であり、特に「事業センス」を身につけることが一つのキーワードとなります。
まず、基本的な考え方として、なぜ今これほどまでに未来を創る人材の育成が重要視されているのでしょうか。中堅企業は、成長のポテンシャルや変化への柔軟性を持つことから、政府も投資拡大や雇用創出、地域経済への貢献といった役割を期待しています。社会からの期待が「外的要因」だとすれば、企業自身の「内的要因」も存在します。予測が難しい時代において、現状維持は衰退を意味するからです。企業が持続的に成長し、未来の事業を築いていくためには、既存事業を守るだけでなく、新しい価値を積極的に生み出せる人材が不可欠です。未来は待っているだけでは来ません。自ら創り出さなければならないのです。
ここで事業センスがキーを握るということです。この事業センスというのは、顧客のニーズと自社の強みとの接点をつかみ、事業を開発して伸ばしていく感性と捉えることができます。単に市場を読むだけでなく、自社のリソースをしっかりと把握して、それをどのように活用すれば顧客価値につながるのかを考えて、具体的な事業を進めてまいります。そのような一連のプロセスを含めて活動してまいります。これは単なるスキルというよりは、総合的な判断力、統合的な能力にあたります。分析力や知識ももちろん必要になりますが、それらを統合してビジネスチャンスを見出し、実行に移していくという嗅覚や構想力といったものが、事業創出の本質にあります。未来を創る人材には、まさにこの感性が中核的な能力として求められるということになります。既存の延長線上ではない何か新しい可能性を発見して実現していくという力です。全体を見て判断する力も必要になります。
これは単に優秀であること以上に、未来を創るという主体性と、新しい価値を生み出す事業センス、この2つが今の時代に求められるリーダー像の核心部分でもあります。では、その未来を創る経営人材には、具体的にどのような資質が必要であるかを説明していきます。まず挙げるのが未来志向、洞察力です。目の前の課題に対応するだけでなく、数年先あるいは長期的な視点で世の中や事業の環境の変化を読み解いて、自社が進むべき方向性を見定める力とも言えます。先を見通すことができなければなりません。だからこそ重要になるのが、戦略的思考と意思決定です。未来への洞察に基づいて、具体的な目標を設定して、それを達成するための道筋を描いて、必要なリソースを配分して、時には難しい決断を下していく、そのような力です。未来を見て、具体的な行動計画に落とし込んで決断する、この2つは表裏一体の関係です。
自社の内部だけでなく、社外に常にアンテナを張ることが大切です。つまり、自分の会社の論理や常識だけにとらわれることなく、広く社会や市場の動向、技術の発展、競合の動きに目を向けて、そこから得た情報を自社の戦略に生かす、そういう視点が不可欠です。内向き思考ではなく、視野の広さが戦略の質を左右します。社外の知見やネットワークを取り込んで活用する力も含まれます。
そしてもう一つ、とても重要な資質として挙げるのが影響力です。リーダーシップ論などでよく聞く言葉ではありますが、自らの言動とリーダーシップで周囲を巻き込み、他者を突き動かす影響力が必要になります。これは、役職や権限に頼って人を動かすトップダウン型のリーダーシップとは少し異なります。むしろ、自らのビジョンや情熱、考え方に対する共感を呼び起こして、周りの人々が自発的に協力したいと思わせ、リーダーについていきたいと思えるような、そういう人間的な魅力やコミュニケーション能力に基づいた力とも言えます。つまり、指示だけでなく、共感でも人を動かす力です。未来を創るような大きな変革は、一人でできるものではありません。周りを巻き込む力は、必要不可欠になります。未来の方向性を示して、戦略的に計画して、そして影響力で人を動かす、これが三位一体となって初めて未来を創るリーダーシップが発揮されます。
未来志向、戦略性、影響力、そのような資質は一朝一夕に身につくものではありませんが、企業はそのような人材を育成していかなければなりません。育成のポイントとして重要なところは、まず育成の基本姿勢として、自分で考え、判断する力を習慣化していくことがとても大事になります。受け身ではなく、自律的に思考して行動する力です。基礎力を培い、自ら考えて動ける人材を育成していきます。そして、何よりも実践経験を積ませることがとても大事になります。
プロジェクトの推進を、若手の頃から数多く任せるという経験が必要になります。未経験な分野であっても、取り組まなければなりません。苦手な分野やまだ未経験な領域にも、取り組まなければなりません。未経験の領域というのは、コンフォートゾーン、つまり快適な領域から意図的に飛び出して、新しい学びや新たな視点の獲得を促す、そのような狙いです。得意なことだけをしていても、思考の幅や経験の幅が限定されてしまいます。あえて未経験の分野も挑戦させるということで、問題解決能力や適応力、そして何より自分で考え抜く力、これらが鍛えられるということになります。
ある程度の負荷をかけて成長を促す挑戦的なアプローチでもありますが、ただ任せるだけでなく、関与の度合いもとても重要になります。プロジェクトメンバーとして参加させるだけでなく、自ら立案、提案し、経営陣に対する説得をして承認を得るまで実行していくように、裁量権や責任の大きい経験を積ませることが効果的です。単なる担当者レベルの仕事だけでなく、経営者目線での経験を与えます。企画立案から予算獲得、関係部署との調整、そして最終的な経営層への説明責任まで経験させるということです。これは、経営感覚を磨くことができ、若いうちからこういう経験を積ませることが大事です。失敗するリスクも当然ありますが、その失敗から学ぶこと自体が貴重な財産になります。そういう考え方が根底にあります。
このような個人の挑戦を支えるためには、組織全体のあり方がとても大事になります。柔軟に対応できる組織体制が不可欠です。各部門がそれぞれ持つ専門知識をもとに、戦略を構築して経営者に意見や相談を重ねるような経営のあり方でなければ、組織は機能しません。単なるトップダウンだけでなく、各部門が主体的に戦略を考えて、経営層と双方向で活発な議論ができるような、そういう風通しの良い組織文化が必要になります。個々の人材が挑戦的な経験を通じて自律的に考え、行動するために、その意見や提案を受け止めて生かすことができる土壌、つまり柔軟でオープンな組織体制が不可欠です。硬直した組織では、せっかくの人材も宝の持ち腐れになりかねません。個人の育成と、それを支える組織のあり方は、車の両輪のような関係にあるということになります。
付加価値の高い人材を大きく2つのタイプで整理していきます。戦略リーダー(経営人材)とプロフェッショナルという分類です。それぞれの役割と育成の方向性を区別して考えることは、効果的な人材育成戦略を立てる上でとても大事になります。戦略リーダーというのは、これまで話してきた未来を創る経営人材そのものです。新しい価値を生み出す全社視点や未来志向を持って事業を推進し、変革できる人材と定義しています。会社全体の舵取りを担って事業を成長させ、あるいは変革をリードしたりする役割を持ち、先ほどの未来志向、戦略性、影響力、これを高いレベルで兼ね備えた人材と言えます。
その一方で、プロフェッショナルという人材は、社内外に通用する付加価値の高い専門性を有した人材です。特定の分野、例えば、技術やマーケティング、営業、法務、そのような分野で非常に深い知識、スキル経験を持っていて、その専門性を武器に組織に貢献する人材です。必ずしも経営全般を見るわけではありませんが、その分野においては、特筆すべき能力が求められ、価値を提供する存在になります。戦略リーダーがオーケストラの指揮者だとすれば、プロフェッショナルは卓越した技術を持つ演奏者みたいなイメージです。重要なことは、どちらが優れているという話ではなく、企業が持続的に成長していくためには両方のタイプの人材が必要であるということです。戦略リーダーが示す方向に進むためには、各分野のプロフェッショナルの高い専門性がエンジンとなります。企業としては自社の事業戦略や組織の状況を踏まえて、どちらのタイプの人材をどのくらいのバランスで育成していくのか、そういうポートフォリオの視点みたいなものが必要になります。
経営戦略と人材戦略はとても密接に連携していかなければなりません。個人の資質や経験、そして組織体制に触れましたが、人材育成をより確実なものにするためには、具体的な仕組みや制度も重要になってきます。個人の努力やOJT任せにするだけでなく、育成を体系的に支援する仕組みの重要性もあります。具体的なツールとしては、スキルマップやチェックシートが挙げられます。個人の能力レベルを可視化するツールでもあります。これらを使って、本人が現在どういうスキルレベルにあって、次にどういうスキルを習得すべきなのか、目標を明確にすることができるわけです。そうしたツールを作るだけでなく、定期的に上司から本人へフィードバックすることが効果的です。目標設定して、進捗を確認して、そして質の高いフィードバックをする、このサイクルを回していくことが成長を促す鍵でもあります。客観的なデータに基づいて上司と部下が対話をして、成長をサポートしていくツールでもあり、コミュニケーションを円滑にする役割も果たします。
さらに、より組織的な仕組みとして、ナレッジマネジメントやタレントマネジメントといったシステム的なアプローチもあります。これは、個々の人が持っている知識やノウハウ、才能など、見えにくい資産を組織全体で共有して有効活用するための仕組みや考え方です。個人の学びや経験を組織全体の力に変えていくためのシステムということでもあります。誰かが異動したり退職したりしても、知識やノウハウが失われにくくなります。そのような目的もあります。属人化を防いで、組織として学習能力を高める効果も期待できます。
このようなツールやシステムを導入するだけで、本当に人材が育つかというと、単純なものでもありません。最も重要となるのが、学ぶ風土の形成です。仕組みや制度とは次元が違う、もっと根源的なものです。風土とは、無自覚に浸透している空気感のようなものであり、その土台には意識的かつ継続的に育んできた価値観が存在します。例えば、挑戦を奨励して、失敗を頭ごなしに責めるのではなく、学びの機会と捉えて、新しい知識やスキルを積極的に学んで、それを共有することを尊ぶことや、役職にかかわらず建設的な意見交換を歓迎する、そういう価値観が経営層から現場の社員まで日々の行動や意思決定の隅々まで浸透している状態です。それが「学ぶ風土」と言えます。いくら立派な研修制度やスキルマップがあっても、失敗を恐れて挑戦しないことや、知識を独り占めしてしまうこと、上司に意見が言えない関係である、そういう雰囲気の会社は、やはり人は育ちにくくなるものです。形だけ整えても、その根底にある価値観、つまり組織文化が伴っていなければ、制度は形骸化してしまう可能性が高いです。
人材育成の成否に最終的に影響するのは、この目に見えない風土になります。未来を創る経営人材を育成するためには、まずどんな人材を育てたいのか考えなければなりません。その要件である、未来志向、洞察力、戦略的思考、意思決定、そして影響力といった資質を明確に定義することが、とても大事になります。そして、それらの資質を効果的に伸ばすために、座学だけではなく、挑戦的な実践経験が必要になります。未経験な分野であってもプロジェクトを任せて、企画立案から経営層への説明まで一連のプロセスを経験させることが重要です。そのような個人の挑戦を可能にして支えるためには、柔軟な組織体制が欠かせません。各部門が主体的に考えて、経営層と活発に議論できる、そういう風通しの良さが求められます。さらに育成をサポートする仕組みとして、スキルマップ、定期的なフィードバック、そしてナレッジマネジメントのようなシステムも有効です。そして、これらの全ての取り組みの土台として最も重要なのが、学ぶ風土の存在です。挑戦を奨励し、学びを尊ぶという価値観が、組織全体に深く根付いていることが大事です。
自分自身のキャリアを振り返り、今関わっている組織や会社の状況を考えたりする上で、新しい視点をこれからも創出していかなければなりません。我々の普段の職場の空気や文化、また当たり前として受け入れているものがあります。それらを作り出している根底の価値観は、一体何か考えてみてください。それは誰かが意図して育んできたものなのか、それとも、無意識のうちに形成されてきたものなのか、自分自身の当たり前の裏側にある価値観について掘り下げて考える必要があります。