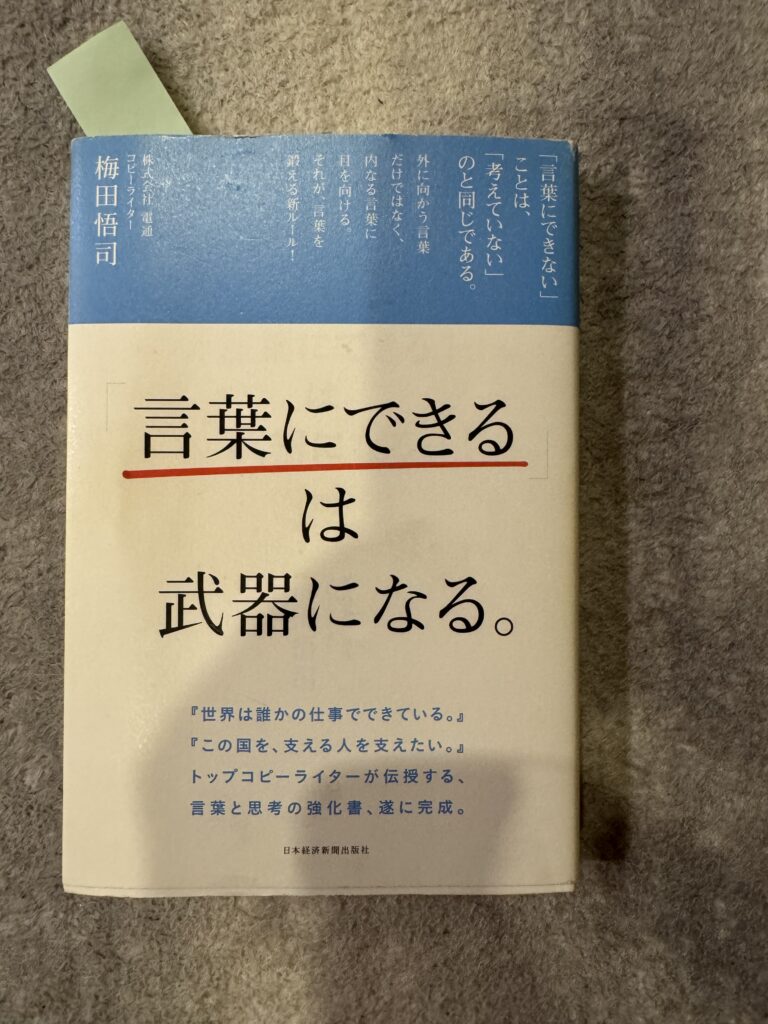251010 言葉にできるは武器になる
私が最近読んだ本の中で、とてもおすすめしている本であります。言葉にできるは武器になる。言葉の定義を、内なる言葉と外なる言葉に分けて考えます。私たちは日々、頭の中で使っているのは、内なる言葉です。これをどう磨いていくのか。そして、それをどう思考を深めて、他の人とのコミュニケーションを変えていく力になるのか。このような点について説明をしていきます。これは、思考力を深めることや、表現力を高めることにつながります。内なる言葉と、どのように向き合っていけばよいか、それを相手に届く外に向かう言葉に変えていくことにつなげていきます。言葉は、何かを伝えるツールだけではなく、自分自身の考え方そのものを形作るものであります。人間関係や自己認識を深めることにも影響を与えます。
はじめに、内なる言葉と向き合うことの重要性について説明していきます。これは、頭の中で考えていること、自分自身と話している言葉と言えます。内なる言葉の質や、その解像度を高めて、豊かさを高めていきます。それが自分の思考の深さにつながります。場合によっては、自分で限界を判断してしまったりしています。人には、相手の言葉に宿る重さや軽さ、深さ、先を通じて、その人の人間性そのものを、無意識のうちに評価をしています。これには、その人の内なる言葉の蓄積が発する言葉の節々に滲み出ることになります。
コミュニケーションを取れるレベルに触れます。相手との①不理解②理解③納得④共感。一番深いレベルが、共感です。この共感レベルの関係を築くには、内なる言葉が豊かでないと、難しいことになります。つまり、自分の考えをもっと鮮明にしたいとか、あるいは誰かに何かを深く伝えたいと思うならば、まずは自分の中にある言葉、つまり内なる言葉の質を高めることから始めなければなりません。普段の自分自身の内なる言葉、頭の中で考えのプロセス、自分の頭の中で考える言葉について、どれくらい自分自身が耳を傾けているのでしょうか。言葉の力について、人を動かす力ではなく、人が動きたいと思わせる力でもあります。強制ではなく、内側からの動機づけを促す力となります。これは表面的なテクニックではなく、磨かれた内なる言葉が生み出す納得感や共感が初めて発揮される力になります。この共感レベルに到達することが本当の意味で言葉を武器にするということになります。
その重要な内なる言葉をどのようにすれば磨いて思考を深められるのか考えていきます。まず頭に浮かぶことを書き出すことが必要です。これはとても単純な作業ですが、とても効果の出る作業です。思考を整理して、客観的に見るための第一歩であるので、とても効果が出ます。頭の中だけで考えていると、どうしても同じところをぐるぐる回ったり、漠然としたままだったりしがちですけど、書き出すことで思考が見える化できるので、自分を知り、内なる言葉を磨かれます。書き出すことにより頭が空っぽになると考える余裕が生まれます。それが、思考のためのスペースを作る行為ということになります。
そして、T字型思考という考え方があります。一つのテーマと考えて、それを内なる言葉に対して、本当にそうか前提を疑います。それから、それでどうする具体的な展開を考えます。また、なぜそうなのか、深掘りをして本質を追求します。この3つの問いかけにより、思考を縦と横に広げて深めていくアプローチ方法です。1つの情報をそのまま受け入れるのではなく、いろんな角度から掘り下げて考えていきます。本当にそうか批判的に考えてどうするか未来や行動につなげて、なぜそうなのか根本的に理解しようとすると、これを繰り返すことで考えが具体的で、しかも本質的になっていくイメージとなります。その他にも、時間軸、認証軸、願望軸、感情軸で考える。これも、思考を立体的にするのに役立ちます。
そして、自分の思い込みから脱すること、自分の壁から解放することがとても大事になります。私たちは、無意識のうちに、常識ではこうだとか、自分の専門性ではこうとか、過去に前例がないからいけないとか、これは苦手だから考えないなど、そういう思考の罠にとらわれがちです。これは常識的、仕事観、専門性、時間、前例、苦手意識といった、見えない壁として存在をしてしまいます。こういう壁があることに、まず気づくこと、そしてそれを意識的に乗り越えようとすることが、思考の自由度を高めて、新しい発想や深い洞察につながっていきます。この壁を認識して挑戦していくことが、前述のT字型思考を含めて、より強烈に思考を深めることになります。普段、思考する上で無意識に使ってしまっている壁は何かそれを特定するだけでも、思考は一歩前に進むことになります。
書き出して、客観視して、T字型思考で深掘りして、多軸思考で多角的に掘り下げて、さらに自分を縛る壁を認識して、それを乗り越えようとする。この一連のプロセスが内なる言葉を豊かにして思考を鍛えるサイクルになるということになります。
このようにして深めた内なる言葉を次にどうやって外に向かう言葉にしていくのか言葉にするプロセスの段階に移ります。ここで大事なのが伝えたい動機の存在です。伝えたい動機が内なる言葉を余すことなく伝える原動力になります。どんなに素晴らしい考えを持っていても、それを届けたいという熱量がないと、なかなか相手の心に響くことはありません。思いが言葉に魂を込める源泉になるわけです。
そしてその思いを効果的に形にするための型として、例える、繰り返す、対比で話す、断定する、感じる言葉を使う、5つの型を理解していきます。ここが重要なポイントは、言葉で自分を大きく見せることや人から良い印象を得ようとすることに使うのは意味がなく、内なる言葉に適切な形を与えるための変換手法として理解すると良いです。つまり、これらの技法というのは小手先のテクニックではなく、自分が内なる言葉として掴んだ本質やイメージをもっと的確に、そして相手と共有できる形で表現するための技法として捉えます。あくまでも内なる言葉を忠実に効果的に伝えるための手段です。
偉人の言葉を引用すると、とても印象的です。「一人の人間にとって小さな一歩だが、人類にとって偉大な一歩である。」これは対比を使うことで、行動のスケールと歴史的な意義を一瞬で伝えています。あるいは、「明日描く絵が一番素晴らしい。」これは断定することで、揺るぎない自信と未来への創造性を感じさせます。「涙は、人間の作る一番小さな海です。」これは、ちょっとした感動した時に出る涙を表現したたとえです。これらの例では、適切な表現がいかに思考や感情を際立たせて、聞き手の想像力を掻き立てることがよくわかります。
そして、こういう技法を使う上で、心得について説明します。
まず、誰一人として平均的な人などいない、一人にでも届ける努力をする、という姿勢です。これは不特定多数に向けた漠然としたメッセージよりも、目の前の一人の人を想像して、その人に届けるつもりで言葉を紡ぐことの重要性を表しています。
一文字でも文字を減らす。余計なものを削ぎ落として本質に迫る簡潔さを意識します。
口に出して読むことで、言葉のリズムを磨き、論理の流れを体で確認することが大事です。
似て非なる言葉を使い分ける。表現の繊細さや知数を深めていきます。知識の量と知恵を活用する力。評価と評判では、客観的な判断と世間の声を使い分ける。意味定義と意義の価値みたいな違いを意識します。
このような言葉のニュアンスの意識が思考の解像度と評価の精度を高めていきます。表現の技法だけでなく,それを支える心構えが,言葉に対する感動を同時に磨くことになります。相手に正確に伝えて,さらに共感を呼ぶためには,この両方が不可欠であります。
普段のコミュニケーションにおいて,内なる言葉で、自分の思考を深めて、技法で言葉を表現して、心構えを持って相手に届ける意識を高める。このようなことを普段から意識すれば、今よりもさらに伝え方が変わることになります。私たちの思考とコミュニケーションの大切さがあり、内なる言葉と外なる言葉の使い分けにより、自分の思考を豊かにして、それをいかに力強い言葉として外に向かう言葉に変えていくのか意識していきます。
自分の内なる言葉と、これに真摯に向き合うことの重要性、そして思考を深めるための具体的なサイクル、書き出すこと、T字型思考、壁を壊すこと、そしてその深めた思いを的確に伝えるための表現方法、それを支えることを心構え、言葉がいかに思考を形作って他者とのつながりを深める上でとても大切な役割を果たしていることが分かります。
「言葉にできるは武器になる」は、自分の考えを研ぎ澄まして、それを相手に的確に伝えて、心を動かす力の強力な推進力となります。普段の生活の中で、意識的に言葉を豊かに、深く、魅力的に考えて、どのような言葉を選ぶのか考えていきます。
偉人の言葉
たとえる
今一度日本を洗濯致し候 坂本竜馬
元来女性は太陽であった 平塚らいてう
リーダーとは、希望を配る人のことだ ナポレオン・ボナパルト
旅は私の学校だ。 自分の目で見、自分の頭で考える マルコポーロ
なみだは人間の作るいちばん小さな海です 寺山修司
反復
もう一歩。いかなる時も自分は思う。もう一歩。今が一番大事な時だもう一歩 武者小路実篤
未来を考えない者に、未来はない ヘンリーフォード
ギャップをつくる。
ひとりの人間にとっては小さな一歩だが、人類にとっては偉大な一歩だ。ニール・アームストロング
努力する人は希望を語り、怠ける人は不満を語る 井上靖
人間は負けたら終わりではない。辞めたら終わりなのだ リチャード・ニクソン
大きな目標があるのに小さなことにこだわるのは愚かだ
ヘレンケラー
楽しいから笑うのではない。笑うから楽しいのだ ウィリアム・シェームズ
言いきる
明日描く絵が一番素晴らしい ピカソ
呼びかけ
困れ、困らなきゃ何もできない 本田宗一郎