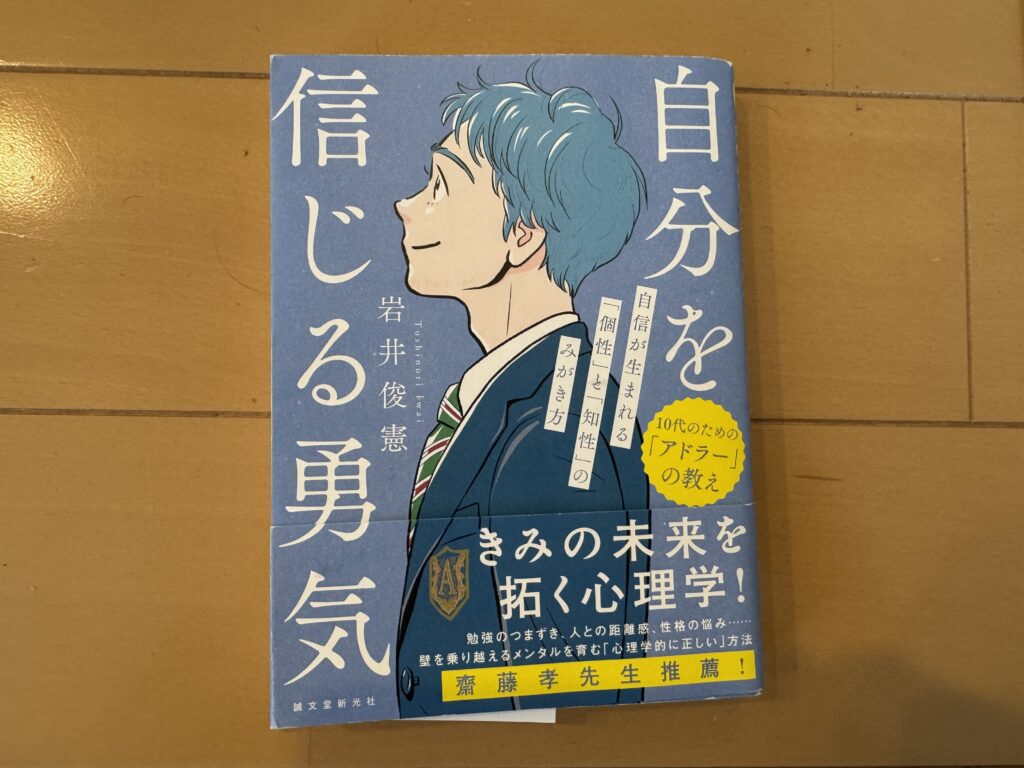251005 自分を信じる勇気
自己信頼や自己理解、そして幸福感それらを見つけるにはどうするかその鍵となる考え方を理解を深めていきます。自分の知性と性格とどう向き合っていくか。それから誰もが持っている劣等感これをどう力に変えていけるのか。そして自己受容と人生の目的を説明します。これらの概念が自分自身の日々の生活と自己信頼に響いていくのか考えていきます。単なる自己啓発のテクニックではなく根本的に自分自身と向き合い方、そしてより肯定的に生きていくための視点、特に自分に何が備わっていて、それをどう活かすかがポイントとなります。
一般的に私たちが考える,IQだけが知性ではありません。問題解決能力や創意工夫、これも立派な知性となります。学校で育むべき要素として尊敬、共感、信頼感、貢献感、
人間関係に関わる力もあります。ハワード・ガードナーの多重性知能理論があります。言語的な知性、対人関係の知性、自分自身を深く理解する内省的な知性など。知性も多様な側面があり,自分自身の強みについて,どのあたりにあるのか考えることができます。今まで知性なんて思ってみなかった部分に光を当てて考えてみるものです。この知性の多様性というのを理解することが、自己理解の第一歩でもあります。自分がどの領域で輝けるのか、それを知ることで、自分が最終的にどうなりたいのか、という自己認識が深まるわけです。それだけではなく、他の人が持っている異なる知性や価値を認めることにもつながっていきます。これが他者への尊敬や共感を自然に育む土壌にもなります。そしてこの自己理解の性格の形成とも密接に関係してきます。
例えば、持って生まれた気質は、内向的か、外向的か、または、育ってきた家庭環境や、家族が大事にしてきた価値観や家族全体の雰囲気、これらが複雑に絡み合ってその人固有の思考パターンや感情の反応、つまり性格を形作っていくということも考えられます。自分らしさを知る良い手がかりになります。知性も性格もまずは。自分を知ることから始まるということになります。
その次に、自分らしさを磨くことに移ります。個性的であることと周りとうまくやっていく協調性のこの2つのバランスが大事になります。そして、セルフトレーニング、つまり自分で努力し続けることの重要性も大事になります。情動を上手にコントロールできる人は、理性と感情を適度に使い分けながら行動できる人であります。
具体的にどういう状態を指しているのか考えます。これは感情に蓋をするのとは違います。感情を無視したり、抑圧したりするのではなく、まず自分の感情をしっかりと認識した上で、その感情に短絡的に反応してしまうのではなく、状況や目的に合わせて理性と感情の。いわば調整する能力が大事になります。感情というとすぐにカッとなって行動に移すのではなく一呼吸置いて考える、そういうことが大事になります。
次にリーダーシップの話も大事です。リーダーシップは誰もが必要であります。いわゆる管理職やリーダーという役職に限った話ではありません。ここで言っているリーダーシップは私たち一人一人が自分の人生という船の船長として主体的に行き先を決めて困難を乗り越えていく力であります。そういう意味合いで捉えています。自分の人生の主導権を握るということです。自分の人生のリーダーです。そのように考えると誰にでも必要な力ということがわかります。
そしてこの自分らしさを、自分の人生のリーダーシップを追求していく上で,多くの人が直面するのが、劣等感の付き合い方です。人は生きている以上、劣等感を抱く存在となります。これは、ある意味、すごく正直なことであります。完璧な人間なんていないからです。他人と比べて感じる劣等感と、あとは自分の中の理想と比べて、感じる劣等感この2種類があります。ここでとても重要なポイントは劣等感と劣等コンペックレックスは分けて考えるということです。
自分はここが足りないと感じる。劣等感自体はむしろ成長へのバネになり自然な感情であります。劣等感そのものが全部悪いというわけではありません。問題になってしまうのはその劣等感が過度に強くなってしまい、そしてどうせ自分なんてみたいな言い訳や、行動しないことにつながり、自分自身のブレーキに使われてしまう、劣等コンプレックスの状態になり、これに陥らないように意識することが大事であります。そのために大事なことは、貢献感を持つことです。つまり、自分は誰かの役に立っているという感覚を持つことが大事になります。
これは、アドラー心理学の中心的な考え方であり、個人の主体性や目的、共同体感覚を重視する心理学にも通じるところがあります。誰かの役に立てているということを感じると、何か自分の価値を感じることにもつながりやすくなります。
自分の努力では変えられないこと、例えば、生まれた環境や過去の出来事、そういうことがあったとしても、
それに対してどう反応してどう意味づけるのかというよりは完全に自分自身の選択できることに主体的な姿勢を持ちそれが劣等感を乗り越える上でとても大事な力になります。変えられないことに囚われるのではなく、変えられる反応や意味づけに焦点を当てること。これが大切になります。
そこで大事になるのが言葉の力であります。普段何気なく使っている言葉が自信に影響するということは、
多くの人が実感していることであります。特に陽性感情,つまりポジティブな感情を意識的に働かせることが大事になります。安心感,期待感,満足感,喜び,興味,感動,愛情,幸福感,このように,リストアップするだけで、とてもたくさんのポジティブな感情があるということを、改めて気づかされます。そして、そのポジティブな感情を引き出す道具というのが、まさに言葉であります。自分自身に向ける言葉、いわゆるセルフトーク、これを意識的にポジティブなものに変えることで、気分や思考もポジティブな方向へ導かれやすくなります。一種の自己暗示のような効果も期待できます。例えば、失敗したときにもうダメだとつぶやく代わりに、よし、ここから何を学べるか考えようと、このほんの小さな習慣の積み重ねが、自己肯定感を育んでいきます。普段からセルフトークを意識してみてください。結構ネガティブなことも言っている人も多いことに気づきます。だからこそ、意識的に変えていく価値があります。
ネガティブな感情の中でも、妬みと嫉妬は区別して考えます。その対処法について考えていきます。妬みと嫉妬は似ているようですけど違います。嫉妬というのは,主に人間関係の中で大切な人との関係が何か脅かされるという感じた時に生まれる感情であります。その感情の存在を認めて、事実を確認して、建設的なコミュニケーションで対応することが大事になります。一方で、妬みというのは、他者が持っているものをこう羨ましく思う感情です。これを単に相手を引きずり下ろしたりしたいという破壊的な方向ではなく、羨望、つまり自分もああなりたいな、自分もあれを手に入れたいなという向上心や目標達成へのエネルギーに転換していくことが大事になります。ネガティブな感情も見方を変えればエネルギーの源になり得るということです。
そして、いろいろな感情や自己認識を得て、次に「自己受容」というテーマにつながります。ありのままの現実、ありのままの自分を受け入れることが、最終的に人生の満足度や幸福度に高めていくということになります。ここで大事なのが、見方を変える発想を転換することの力であります。同じ出来事や、同じ自分の弱みであっても、捉え方次第で、悩みや短所が可能性やユニークな魅力へと変わっていきます。
例えば、頑固ということは、意志が強いと転換できます。飽きっぽいということも、好奇心旺盛なんだなというふうに捉え直すこともできます。これをリフレーミングと呼びます。この視点の転換、発想の転換ができるようになると、今までは、これは自分の性格だからと言って避けてきたことであっても、少し挑戦してみようかな、そのような勇気が湧いてくるかもしれません。結果として、生き方そのものがより肯定的になって可能性が広がっていきます。自己受容は、自己肯定感を育むための大切な土台とも言えます。
そして、その自己受容を土台にして、今度は未来を描いていく人生のシナリオについても考えていきます。自分の中には無意識のうちに描いている究極目標地点、つまり理想の自分像みたいなものがあります。そして、その魅力的な未来の自分に到達するために、今この瞬間に何をすべきか、何を積み重ねていくべきか、考えることが重要になります。
未来志向的で何か希望を感じさせる考え方です。ここでポイントなのは、その究極目標については必ずしも具体的で達成可能な短期目標とは限らないということです。むしろ人生の羅針盤みたいな大きな方向性を示すものでありますから、そこに至るための長期目標や中期目標、短期目標というのは状況の変化とか自己理解が深まりに応じて、柔軟に見直ししたり変更したりしても構いません。
何か固定的な計画に縛られたりするのではなく、大きな方向性を見失わずに、しなやかに進んで対応していくイメージです。柔軟に変更しても構いません。計画は必ずしも予定通りいくことがすべてではありません。
そして、ここでもまたセルフトークが鍵になってきます。未来の理想の自分を思い描いて、それに向かって進み、自分を励ますような言葉をかけます。これが日々のモチベーション維持や困難に立ち向かう勇気から来ます。
自分を励ます言葉が大切です。そして、自分だけではなく、他者との関係における勇気づけ。これも重要な要素として挙げられます。リスペクトをすること、それから共感すること、信頼する、そして協力する、こうした関わりが良好な人間関係を築くだけでなく、巡りに巡って自分自身の価値を感じて、自己価値観を高めて、幸福度を高めることにつながります。
プラスのイメージを掛け算でアップしていくイメージも良いです。ポジティブな関わりが相乗効果でどんどん良い循環を生み出していくイメージになります。そして具体的な行動指針として,示しているのが、誰かに必要とされていると感じることです。それを自分にできる範囲でやること。そして、今更遅いなんて思わずに今から始めること。非常に前向きで実践的な考えです。貢献感にも直結する考え方であります。今からやる、何を始めるにしても遅すぎることなんてありません。そして本当に大切なことは、自分が持っているもの、自分に残されているものは何かを考えることであります。
パラリンピックの創設に尽力したルード・ヴィヒ・グッドマン博士の「失われたものを数えるな。残されたものを最大限に活かせ。」この言葉は、事故などで身体的な機能を失った選手たちに向けられた言葉でありますが、我々全員に当てはまる普遍的なメッセージでもあります。次に、アルフレッド・アドラーの言葉。「重要なことは、人が何をもって生まれたかではなく、与えられたものをどう使いこなすかである。」この言葉は、持って生まれた才能とか、環境、あるいは過去の経験といった、「与えられた」そのものよりも、それを自分がどう解釈して、どう活用していくか、その使い道こそ人生を豊かにすることに鍵があるということを意味しています。失われたものではなく、残されたものに目を向け、与えられたものをどう使いこなすかこれは自己信頼と幸福への道筋を示す根本的な哲学であります。
知恵の捉え方、劣等感との建設的な向き合い方、自己受容の力、そして何よりも、今、ここから自分に与えられたものを最大限にいかしていきます。自分自身に与えられたものは何か。それは才能かもしれないし、経験かもしれない。あるいは、特定の価値観や人間関係かもしれません。その中で、今日から特に意識して活用したいなと。あるいは、これからもっと育てていきたいと感じるもの。何かあるはずです。自分自身の内面を見つめてみることが大事です。内省的な知能を働かせること自体が、自分を信じる勇気を育むための確かな第一歩になります。