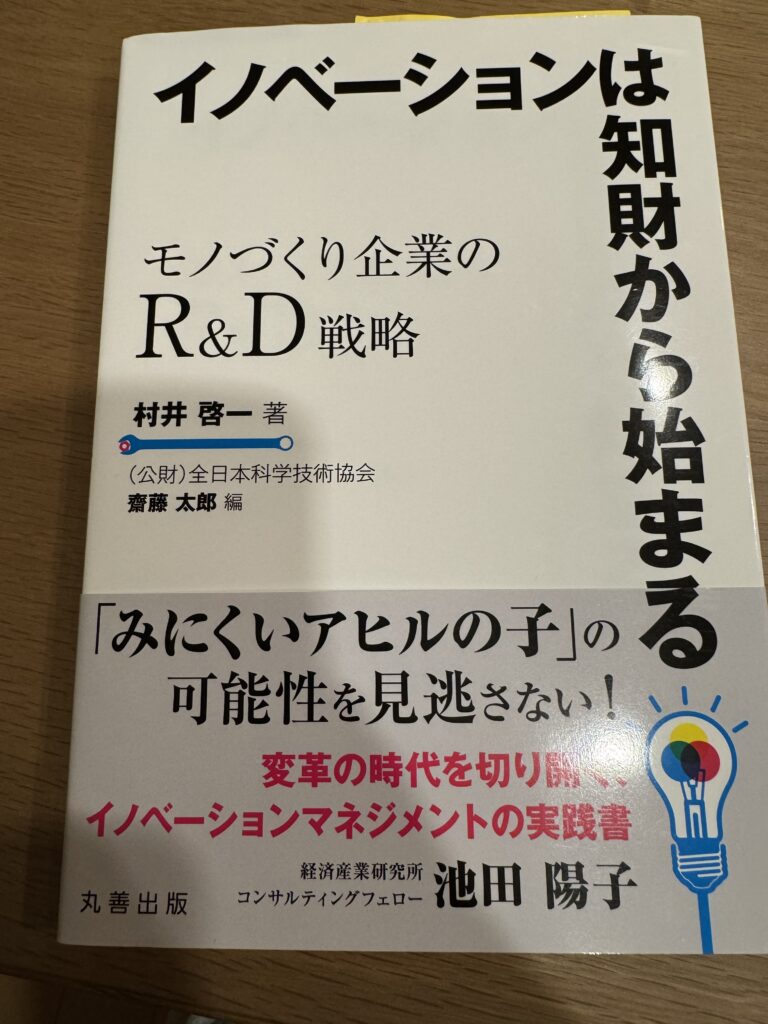251101 イノベーションは知財から始まる
イノベーションをどのように生み出し、そしてどのように育てて、最終的に企業の持続的成長につなげていくか、そのために知的財産戦略やマネジメント、そして,リーダーシップのあり方について考えなければなりません。研究開発や事業戦略に関わる人たちはもちろん、新しい価値創造のプロセス自体に目指している人にとって必要な話となります。
企業の持続的成長のためには、絶対欠かせないものがイノベーションであります。既存事業を伸ばすだけではなく、新規事業を創出して、この2つが車の両輪のように必要であります。イノベーションには2種類あります。1つは、既存のものをより良く改善していく考えに近い連続的イノベーションであります。もう一つが、全く新しい分野を切り開くような非連続イノベーション、いわゆるブレイクスルー型であります。非連続イノベーションにおいては、初期の段階では、既存の枠組みや、常識からすると想定外の考えかもしれませんが、また組織の外にあるように見えることが多いかもしれません。また突拍子もないアイデアにも思えてしまうことが多いです。ここに落とし穴となるものが存在してしまいます。コンピテンシートラップという考えです。
過去の成功体験や自分たちの得意なことに固執してしまうあまり、その想定外や範囲外に見える新しい技術やビジネスモデルの可能性をうっかり見逃してしまいます。柔軟な思考で考え抜くことがとても重要になってきます。柔軟な思考で捉えた新しい発想を既存の知見や技術と結びつける新結合によりイノベーションを創出していきます。これを社会課題の解決の目的につなげて考えていくこと、これこそがイノベーションの本質であります。しかし、誕生したばかりのアイデンティティは非常に壊れやすいという側面もあります。周りの風当たりが強かったり、なかなか理解が得られなかったりすると簡単に消えてしまうというような、そのような儚さを持っています。その壊れやすいイノベーションの種を企業としていかに守って、育てて、そして方向づけていくのか。そこで企業の理念や,ビジョンが重要になってきます。私たちは何のために存在して、どこへ向かうとしているのかという最も根本的な問いかけが必要になってきます。
このビジョンは、一度決めたらそれで終わりではなく、状況に合わせて変化していくし、常に語り継がれていくべきものであります。それが組織全体の羅針盤になり、戦略を進めていくことになります。その戦略を実行して競争優位を築いていくために、強力な武器として登場するのが特許です。特許の本質の力は排他性にあります。他者を排除できるという点です。これを戦略に活用することで、競合に対する参入障壁を築いて、自社の事業領域を守ったり育てたりすることが可能になります。単に発明を守るだけでなく、企業の戦略的な意味合いが持つことになります。他社との違いをどう作るかという点において考えていきます。
次に、コアコンピタンスについて説明します。コアコンピタンスは、他者が簡単に真似できない自社ならではの特徴を表し、強みということです。これをはっきりさせることが、独自性を打ち出す鍵になります。そのために、自分たちの本当の得意分野、技術、コア技術、これが何かということを深く客観的に理解していくことが必要不可欠になります。そして、そのコアコンピタンスやイノベーションの根源には常にサイエンスがあるということを忘れてはなりません。
ここでいうサイエンスは、実験の科学という意味だけではなく、もっと広い意味で捉えます。社会課題の解決につながる本質的な探求や基礎研究のことを表しています。ここでの発見や発明が特許になって、それが事業競争力を生み出し、最終的に企業の持続的成長を支えていくという、そのようなつながりとなります。イノベーションの重要性、戦略的な位置づけをもとに、それを組織の中でどうやって生み出して活性化させていくのか。
ここで逆説的に考えていきます。イノベーションは管理すればするほど生まれにくくなるという性質があります。これはマネジメントの常識からすると相反するものであります。まさにそこがイノベーションマネジメントの,難しさであり、特徴でもあります。マネジメントのやり方は、アイデアを探求する研究フェーズと、製品化を目指していく開発フェーズでは異なります。特に初期の研究フェーズでは、トップダウンで管理するのではなく、多様なイノベーションの芽が自由に生まれて育つような環境づくりが必要になります。新しいアイデアを持っている人は、管理されたいわけではなく、自分のやりたいように試したいという内発的動機を持っています。
多くの研究開発組織が陥りがちな課題が、管理型マネージャーや支配的リーダーの存在がイノベーションのある意味大きな阻害要因になり得るということがあります。部下を自分の思った通りに動かそう、コントロールしようとする姿勢がかえって才能の目を摘むんでしまいます。その対極にあるのが、部下が自ら考え、行動するということを心から信頼するマネージャーの姿勢であります。部下の主体性、才能や才覚、能力を信じて任せるということです。そうすると、驚くことに、マネージャーが想定している以上の成果につながることが往々にしてあります。管理支配から、信頼・エンパワーメントへの転換こそが、イノベーションを解き放つ鍵であるということです。
信頼して任せるだけではなく、リーダーにはさらに能動的な役割も求められることになります。困難があっても諦めずにやり遂げる力、課題、障害を乗り越えて実現する力も必要であります。そこが,リーダーシップの求められるものになります。選択理論心理学に基づいて、人の行動は、罰や報酬みたいな外部から得るものではなく、内側の要求によって動機づけられるという視点で考えます。イノベーションを促進するリーダーの資質を上げていくために、まずリーダー自身のあり方や,姿勢に関わることについて、例えば、物事の本質を常に追求する探究心や本質への追求、それから困難な状況でもユーモアを忘れずに気分転換ができるしなやかさやおおらかさが大事になります。そして、懐が深く厳しいけれども温かいこと。高い基準を持ちながらも、人間的な温かみで人を包み込んで支える力も求められます。周囲の人、人の意欲を引き出して生かす、そういう人間力みたいなものが必要になります。
風土改革は、まずリーダー自身が変わることから始まります。本人が実践していかなければ、組織には響くものではありません。風土改革の目的は、組織全体で,ビジョンやミッションを共有して、社員一人一人のエネルギーの方向性を揃えるベクトルの一致を図ることであります。それを通じて、自律的に考えて行動できる自律人材を育成して、組織全体を活性化させていきます。そのために、リーダーの求められる具体的な行動について、例えば、コミュニケーションの面について、ビジョンを常に未来を語り続けるという情熱と客観性も必要になります。そして、一方的に話すのではなく、関係者の話を聞く耳を持って一緒に考えて、相手への興味と関心、共感を示し、同じ目線で議論することが大事になります。
さらに、メンバーの可能性を最大限に引き出すための行動として、まずは、行動してみようと挑戦を促して、失敗も許容する姿勢でやってみようという精神も大切になります。多様性を尊重して、人材にレッテルを貼ることなく、自分自身の言動が時には意図せず相手を傷つける可能性、つまりハラスメントにつながるかもしれないということを自覚して、常にチェックする謙虚な姿勢も大切になります。それぐらい自己認識が重要になるということであります。求められるリーダーシップ像については、いわゆる人を管理して統制するタイプのリーダーとは性質が異なります。むしろ、個々の可能性を信じて、人が自律的に活躍できるような環境や文化を作り出すことに焦点が当たることになります。
個々のリーダーの資質や行動はもちろん重要でありますが、それだけでは十分ではなく、組織全体の仕組み、いわばイノベーションを生み出すためのエコシステム(自然にバランスと調和をとれる環境)を構築することも不可欠であります。例えば、短期的な利益目標を示す経営指標と、長期的な視点が必要な研究開発、マネジメントをどう連携させるか、この関係性をしっかりと理解して適切に設計することが、持続的成長のために欠かせません。それから、創造性を刺激するカオス、つまりある程度の自由さや混沌とした状態と効率的な実行に必要な秩序、この両方のバランスを取るという高度なマネジメントも求められます。自由な発想を奨励しつつも、無秩序に陥らないための仕組みが必要になるということです。その土台となるのが、適切な組織風土の醸成となります。常に学び続けて、変化に適応していく学習する組織であり、実行や実践が伴います。人材育成に投資にも奨励して、そして組織の目標と個人の成長をしたいという欲求がうまく重なり合うように、関係性の整合性を取るコミュニケーションが日常的に行われていることが大切になります。これらがそろって初めてイノベーションが継続的に生まれていくということになります。
そして、目指すべき最終的な姿というのは、自律的な人材による活発な研究開発がダイナミックに推進される組織ということになります。活発な研究開発というのは、トップからの指示待ちに頼るのではなく、現場の多様な知見やアイデアが活発に議論されて、試されて、育てられていくことになります。そのような生命力あふれる組織像が大事になってきます。イノベーションは決して運任せや、偶然の産物ということではありません。まず、企業の理念やビジョンに根ざした戦略的な基盤があって、自社の差別化があり、そして人を管理するのではなく、信頼して可能性を引き出すマネージメントスタイルが必要であり、さらにそれを下支えする人間的な温かみを持って学習と挑戦を促すようなリーダーシップがあり、そうしたリーダーシップによって育まれた組織文化が土台として必要になります。